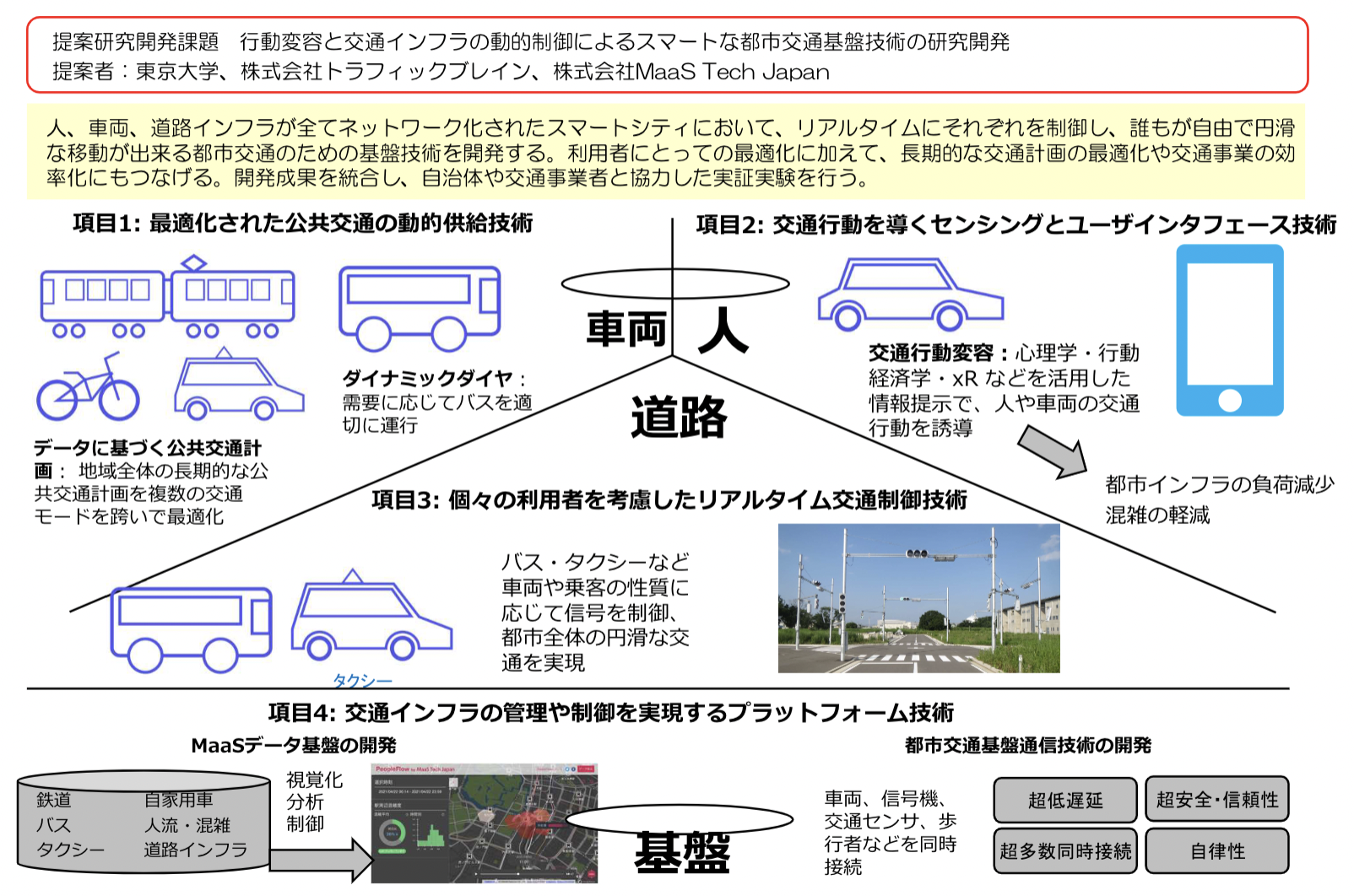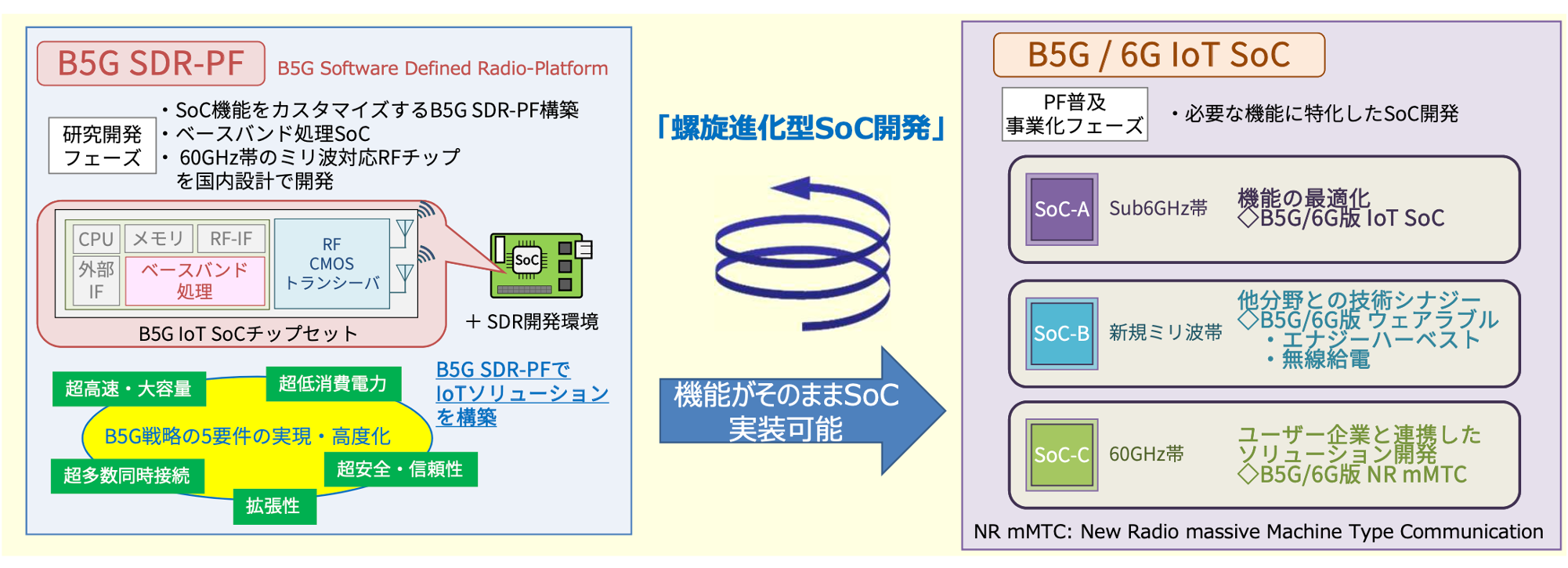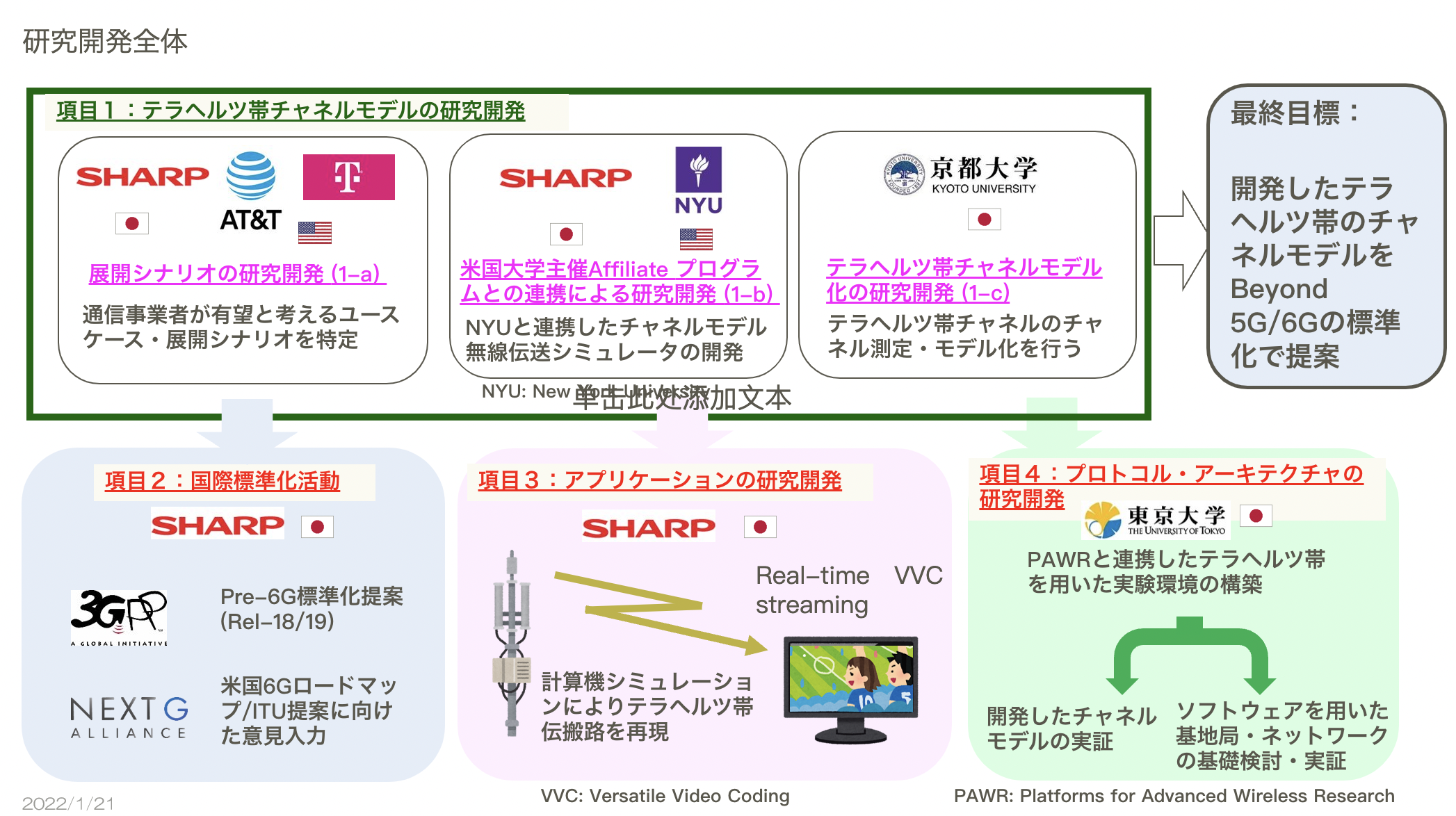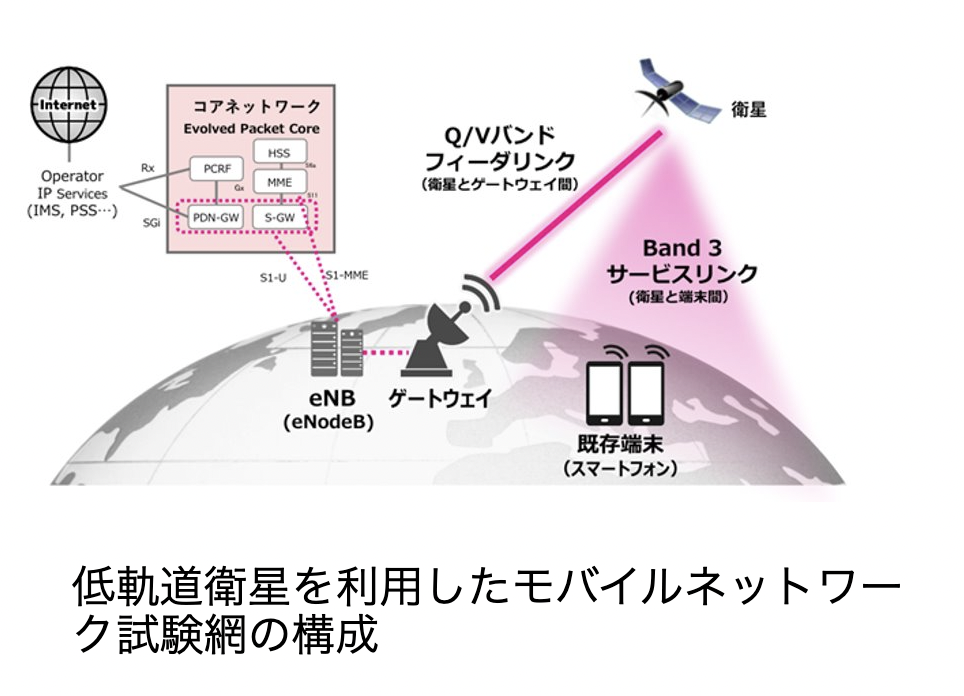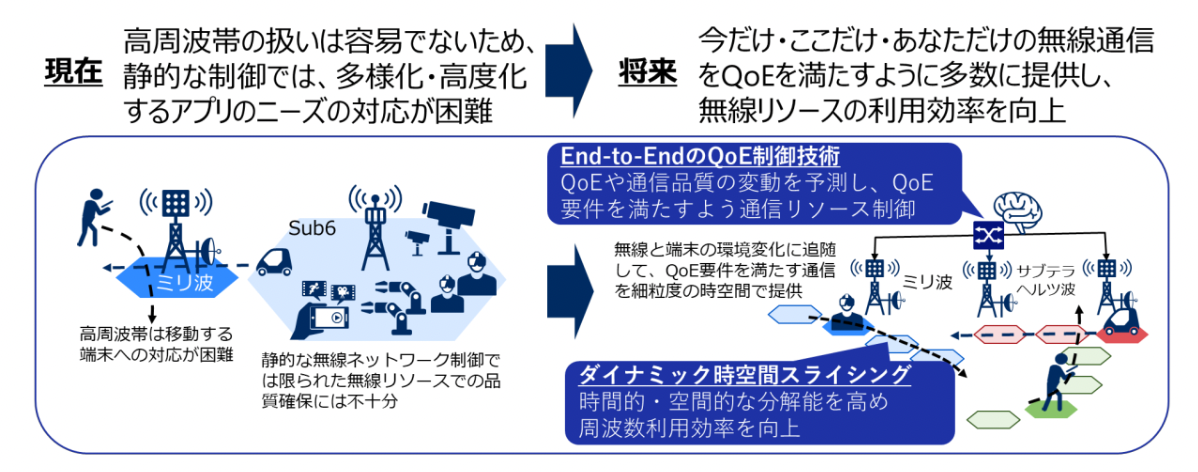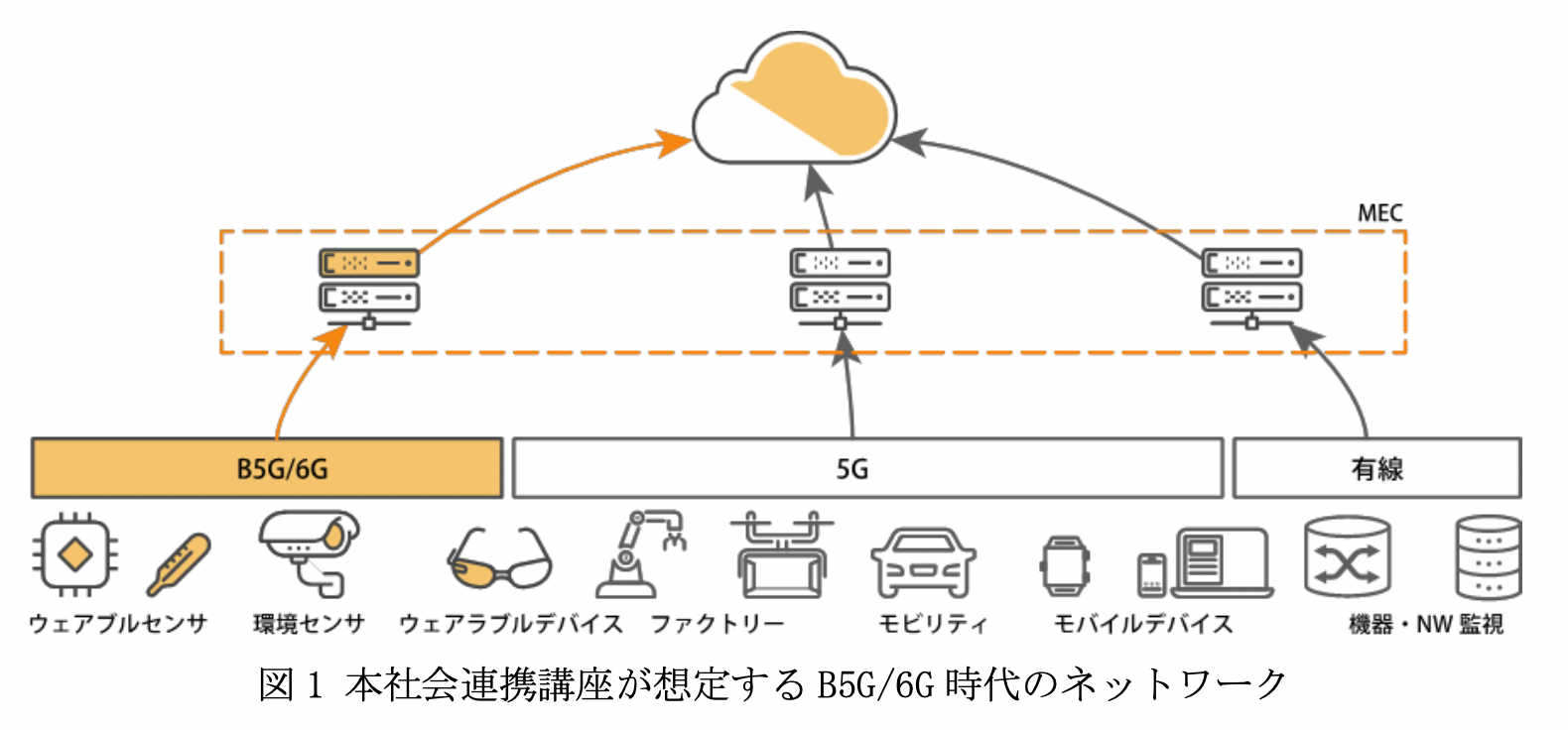日・フィンランドBeyond 5G/6G共同セミナーを開催「デジタル化の社会的インパクト ~Beyond 5Gの推進に向けて~」
令和4(2022)年5月11日(水)に日・フィンランドBeyond 5G/6G 共同セミナー「デジタル化の社会的インパクト~Beyond 5Gの推進に向けて~」が、総務省と在京フィンランド大使館共催、東京大学を後援とし安田講堂にて開催されました。
フィンランドのサンナ・マリン首相の来日に合わせて、両国間の連携を強化すると共に、我が国のBeyond 5G/6Gの推進に向けた国際連携の取組を加速することを目的として開催された本セミナーでは、総長による開会挨拶、サンナ・マリン首相および竹内芳明総務省審議官による基調講演の他、Beyond 5G/6G分野での今後の両国の連携をテーマとしたパネルディスカッションなどが行われました。
なお、本セミナーはBeyond 5G推進コンソーシアム関係者およびフィンランド政府関係者を対象とし、ハイブリッド形式で実施されました。オンライン配信には400名程度、対面参加には200名程度から参加登録がありました。
(東京大学HP2022年6月8日掲載「日・フィンランドBeyond 5G/6G 共同セミナー「デジタル化の社会的インパクト~Beyond 5Gの推進に向けて~」より引用)